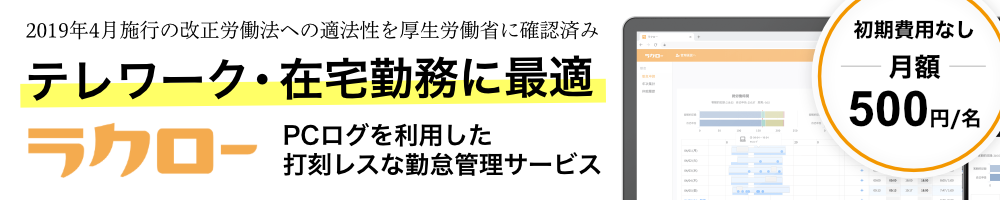「勤怠管理」は、単なる出退勤の記録にとどまらず、コンプライアンス、従業員の健康、そして正確な給与計算の基盤となる重要な業務です。
本記事では、なぜ勤怠管理が重要なのか、そして具体的にどのような点に注意して管理すべきなのかを解説していきます。
勤怠管理が必要な理由
なぜ、企業は従業員の勤怠を管理する必要があるのでしょうか。その理由は、大きく分けて3つあります。
1.法的義務のため
まず、労働安全衛生法という法律によって、企業に従業員の労働時間を客観的に把握する義務が課されているためです(労働安全衛生法第66条の8の3、労働安全衛生規則第52条の7の3)。
これに違反した場合、直接的な罰則規定はありませんが、労働基準監督署からの是正勧告の対象となります。また、労働時間の把握を怠った結果、後述する過重労働や未払い残業代の問題が発生した場合、労働基準法違反として罰則(30万円以下の罰金など)が科される可能性があります。
労働時間の把握は「客観的な方法」で行う必要があるとされていますが、具体的には、使用者(会社)が自ら現認する方法や、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録といった客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することを指します。単なる自己申告だけでは、原則として認められない点に注意が必要です。
2.正確な給与計算のため
勤怠管理は、従業員の給与を正確に計算するための根拠となります。給与には、基本給などの毎月一定のものだけでなく、時間外労働、休日労働、深夜労働などに応じて変動する割増賃金もあります。これらの割増賃金は、労働基準法で定められた割増率に基づき、1分単位で計算・支給する必要があります。
もし勤怠管理が杜撰であれば、未払い残業代が発生するリスクが高くなります。未払い残業代は、従業員からの請求があった場合、遅延損害金や付加金(未払い額と同額)とともに支払いを命じられる可能性があり、企業の経営に大きなダメージを与えかねません。また、従業員との信頼関係を損なう原因にもなります。正確な勤怠記録は、企業と従業員双方にとって不可欠です。
3.過重労働防止のため
勤怠管理は、従業員の心身の健康を守るためにも極めて重要です。長時間労働は、脳・心臓疾患のリスクを高めるだけでなく、メンタルヘルス不調の原因にもなります。
企業には、従業員に対する安全配慮義務があります。これは、労働契約法第5条に定められており、企業が従業員の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務です。
労働時間の状況を正確に把握することで、特定の従業員に業務が偏っていないか、時間外労働が法定の上限(原則月45時間、年360時間)を超えていないかなどをチェックできます。長時間労働の兆候を早期に発見し、業務量の調整、人員の補充、医師による面接指導の実施といった適切な措置を講じることで、過労死といった最悪の事態を防ぐことができます。
勤怠管理が必要となる従業員
勤怠管理の対象となるのは、どのような従業員なのでしょうか。
1.結論
結論として、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、すべての従業員が勤怠管理の対象となります。
2.管理監督者
労働基準法第41条に規定される「管理監督者」は、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外されます。そのため、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払いは不要です。
この点から、「管理監督者の場合は勤怠管理が不要」と思われがちですが、ここで注意すべき点が何点かあります。
①健康確保の観点
働き方改革の一環として、2019年4月より、会社は面接指導を実施するために労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされています(労働安全衛生法66条の8の3)。ここにいう労働者から管理監督者は除外されていないため、健康確保の観点から労働時間の状況を把握することが義務付けられていることになります。
②安全配慮義務の観点
会社には、労働者に対する安全配慮義務があります(労働契約法5条)。これは管理監督者に対しても適用されるものであり、管理監督者であっても、長時間労働が常態的になっている等の事情があり、会社がその対策を講じていないような事情がある等の場合には、安全配慮義務違反が問われる可能性があります。
③深夜労働の割増賃金は必要
管理監督者であっても、深夜労働(午後10時~午前5時)に関する規定は適用されるため、この時間帯に勤務した場合は深夜割増賃金の支払いが必要です。この割増賃金の未払いを防ぐためには、適切な勤怠管理が必要となります。
3.裁量労働制
裁量労働制は、実労働時間にかかわらず、労使であらかじめ定めた時間(みなし労働時間)だけ働いたものとみなす制度です。専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2種類があります。 さきほどの管理監督者と似た認識で、「あらかじめ定めた時間労働したものとみなして賃金を計算するから勤怠管理は不要」と思われがちですが、ここでも注意すべき点が何点かあります。
①健康確保の観点
管理監督者と同様に、健康確保の観点から労働時間の状況は把握しなければなりません。
②安全配慮義務の観点
管理監督者と同様に、会社は裁量労働制の対象者に対しても安全配慮義務があります。
③深夜・休日労働の割増賃金は必要
1日のみなし労働時間が8時間以内の場合、法定時間外労働は発生しませんが、深夜に働いた場合や、法定外休日(週40時間超)、法定休日に働いた場合には、それぞれ割増賃金の支払いが必要です。これらの割増賃金の計算・支払いには、適切な勤怠管理が必要です。
4.事業場外労働のみなし労働時間制
事業場外労働のみなし労働時間制とは、外回りの営業職など会社の外で業務に従事し、労働時間を正確に算定することが難しい場合に、所定労働時間などあらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
この制度も「みなし労働時間で賃金を計算するから勤怠管理は不要」と思われがちですが、管理監督者や裁量労働制と同様に、注意すべき点があります。
①健康確保の観点
管理監督者・裁量労働制と同様に、健康確保の観点から労働時間の状況は把握しなければなりません。
②安全配慮義務の観点
管理監督者・裁量労働制と同様に、会社は事業場外労働のみなし労働時間制の対象者に対しても安全配慮義務があります。
③深夜・休日労働の割増賃金は必要
みなし時間が適用される場合でも、実際に深夜に働いた場合や、法定休日に働いた場合には、それぞれ割増賃金の支払いが必要です 。これらの割増賃金の計算・支払いには、適切な勤怠管理が必要です。
なお、そもそも論になりますが、事業場外労働のみなし労働時間制については、それが適用可能であるのかどうかという論点があります。現代においてはスマートフォンなどで勤怠管理を行ったり上司と連絡を取ったりすることが容易になっており、そもそもこの労働時間制を適用することができるのかという点には留意が必要です。
以上の点から、すべての従業員において勤怠管理は必要となります。
勤怠管理でチェックすべきポイント
では、具体的に勤怠管理のどのような項目をチェックすればよいのでしょうか。最低限、以下の4つのポイントは必ず確認するようにしましょう。これらのポイントそれぞれにおいて、実態と乖離がないか、気になる点がないかを意識しながら確認します。
1.始業・終業時刻、労働時間、休憩時間
最も基本的な項目です。従業員が何時に仕事を始め、何時に終えたのかを記録します。これにより、その日の実労働時間が確定します。
始業・終業時刻
タイムカードの打刻時刻やPCのログイン・ログアウト時刻などが、業務の実態と乖離していないかを確認します。例えば、打刻後にサービス残業を行っていないか、朝礼などが労働時間に含まれているか、といった点に注意が必要です。
労働時間
1日の労働時間が長時間になっていないか、実態と乖離していそうなものはないかを確認します。
休憩時間
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が、労働時間の途中に適切に付与されているかを確認します。休憩時間が取得できていない、あるいは電話番などで実質的に休憩できていないといった状況は問題となりますので注意が必要です。
2.時間外労働時間、深夜・休日労働時間
割増賃金の計算に直結する重要な項目です。
時間外労働時間
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間です。月ごとの時間外労働時間を集計し、36協定で定めた上限時間を超えていないかを確認します。
深夜労働時間
午後10時から午前5時までの間の労働です。この時間帯に勤務した場合は、通常の賃金に加えて2割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。
休日労働時間
労働基準法で定められた法定休日(週1日または4週4日)に労働した場合です。3割5分以上の割増賃金の支払いが必要となります。
3.出勤・欠勤日数、休日出勤日
給与計算期間の勤務状況を把握するための項目です。
出勤・欠勤日数
欠勤日数により、給与計算において欠勤控除の計算が必要になることがあります。また、あまりに欠勤が多い従業員がいる場合、健康上の問題や職場環境の問題を抱えている可能性も考えられるため、面談などのフォローアップが必要になる場合もあります。
休日出勤日
どの日に休日出勤したかを明確に記録します。併せて、振替休日や代休の付与がある場合には、その管理も必要となります。
4.年次有給休暇、その他の特別休暇
休暇の取得状況を管理し、従業員の権利を守るための項目です。
年次有給休暇
年次有給休暇の取得日数、残日数を正確に管理します。2019年4月からは、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、年5日の年次有給休暇取得が義務化されました。会社は、各従業員の取得状況を把握し、取得日数が5日に満たない従業員に対しては、時季を指定して取得させるなどの対応が必要です。
その他の特別休暇
慶弔休暇や夏季休暇など、会社が任意で設けている休暇の取得状況も管理します。就業規則の定めに従って、適切に運用されているかを確認します。
多様な働き方に対応する、勤怠チェックの重要ポイント
ここまでは全ての従業員に共通する基本的なチェック項目を解説しました。
しかし、働き方が多様化する現代においては、画一的な確認だけでは不十分なケースも増えています。ここでは、特に配慮が必要となる代表的な3つの場面における勤怠チェックのポイントを解説します。
1.労働時間制度の違い
従業員に適用されている労働時間制度によって、チェックすべきポイントが異なりますので、注意が必要です。
固定労働時間制
1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えていないか、休憩は適切か、といったチェックを行います。また、1日の所定労働時間が8時間未満である場合には、所定外労働時間と法定外労働時間のカウントが適切かも併せて確認します。
変形労働時間制
1日単位や週単位で法定労働時間を超える日(週)があったとしても、直ちに違法とはなりません。1日ごとの確認も重要ですが、対象期間全体を平均して、週40時間以内に収まっているかという点の確認も重要です。日々の労働時間に加え、月単位、年単位での総労働時間の管理が重要になります。変形労働時間制は他の労働時間制度に比べて勤怠管理が複雑になりますので、制度の理解とシステムをうまく活用できるかがとても重要になります。
フレックスタイム制
日々の始業・終業時刻が従業員の裁量に委ねられているため、基本的に遅刻や早退という概念がありません。チェックすべきは、「清算期間」(一般的には1ヶ月が多い)の総労働時間が、所定の労働時間(法定労働時間の総枠)を満たしているか、あるいは超過していないかです。また、コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)が定められている場合は、その時間帯に勤務しているかの確認も必要です。よくあるケースとして、フレックスタイム制を採用しているにもかかわらず、固定労働時間制のように勤怠管理していることがありますので、注意が必要です。
裁量労働制
裁量労働制の場合、実労働時間ではなく「みなし時間」で管理されますが、裁量労働制=割増賃金不要と認識されているケースがあります。しかし、裁量労働制であっても、深夜労働や法定外休日労働(週40時間超)、法定休日労働は割増賃金の対象となることは前述のとおりです。そのため、深夜時間帯(22時~5時)や法定外休日、法定休日に勤務しているかどうかという点は、他の労働時間制と同様しっかりとチェックする必要があります。
このように、労働時間制度によってチェックすべきポイントは異なります。適用される制度を正しく理解し、それぞれのルールに沿って勤怠データを確認することが、適切な労務管理の第一歩となります。
2.テレワーク
テレワーク(在宅勤務)は、従業員の姿が直接見えないため、勤怠管理の難易度が上がります。特に注意すべきは「労働時間の客観的な把握」と「中抜け時間」の扱いです。
労働時間の客観的な把握
従業員の自己申告だけに頼ると、サービス残業や、逆に不必要な残業が発生しやすくなります。これを防ぐため、PCのログオン・ログオフ時刻の記録、勤怠管理ツールの導入、業務開始・終了時のチャットやメールでの報告ルールの徹底など、客観的に労働時間を把握する仕組みが重要になります。
中抜け時間の管理
テレワーク中は、業務の途中で私用(役所の手続き、子供の送迎、通院など)のために業務を離れる「中抜け」が発生しやすくなります。労働から離れている時間は休憩時間として扱い、労働時間に含めないのが原則です。中抜けの時間を正確に記録・控除できるよう、勤怠システム上で中抜けの開始・終了を記録する、あるいは事後に報告するといったルールを明確に定めておく必要があります。その際、1日の休憩時間の合計が法定の休憩時間(6時間超で45分、8時間超で1時間)を下回らないよう注意が必要です。
オフィス勤務とは異なる環境であることを前提に、性善説に立ちつつも客観性を担保できるルール作りが、テレワークにおける勤怠管理の鍵になるものと考えます。
3.年収の壁
いわゆる「123万円・150万円・160万円の壁」(所得税)や「106万円・130万円の壁」(社会保険)などを意識し、扶養の範囲内で働くことを希望する従業員は少なくありません。
日々の勤怠をチェックし、月々の給与額を把握することで、その従業員の年収が、年末に扶養の範囲を超えてしまいそうかを予測することができます。もし超過しそうな場合には、早い段階で本人にその事実を伝えることで、今後の働き方(シフトの調整など)について相談する機会を設けることができます。
もちろんこれは企業の法的な義務ではなく、従業員個人で管理すべきことともいえますが、対応できると、従業員のライフプランに寄り添う配慮になると考えます。何も伝えずに年末を迎え、「気づいたら扶養から外れてしまい、手取りが減ってしまった」などという事態になれば、従業員の不満や離職にも繋がりかねません。
勤怠データを活用して従業員の働き方をサポートすることも、勤怠管理の重要な役割の一つと言えるのではないでしょうか。
まとめ
勤怠管理は、単なる事務作業ではありません。法律を遵守し、正しい給与計算を行い、そして何よりも従業員の健康と安全を守るための、経営の根幹をなす重要な業務です。
しかし、フレックスタイム制やテレワークといった多様な働き方が広がる現代において、本記事で解説したようなチェックポイントを表計算ソフトや手作業だけで正確に管理・運用することは、困難になり、労務担当者の大きな負担となっています。
そこで有効となるのが、勤怠管理システムの活用です。ICカードやPCログなどと連携できるシステムを導入すれば、労働時間を客観的かつ正確に記録することができます。これにより、手作業による集計ミスや不正な申告を防ぎ、複雑な割増賃金の計算も自動化することができるため、管理業務の大幅な効率化が図れます。さらに、リアルタイムで労働時間を可視化できるため、長時間労働の兆候を早期に発見し、従業員の健康障害を未然に防ぐためのアクションに繋げやすくなります。
ただし、システムを活用する際は、その設定を正しく行うことがとても重要になります。システムの設定がそもそも正しく行われていないために、勤怠管理がスムーズに行えなかったり、未払い残業代が発生してしまったりするケースもよくありますので、この点には注意が必要です。
適切な勤怠管理は、従業員との信頼関係の礎です。システムもうまく活用し、企業の持続的な成長を目指しましょう。
打刻レス勤怠管理ツール「ラクロー」のご紹介
弊社の打刻レス勤怠管理ツール「ラクロー」は客観的記録をベースに把握した労働時間を、従業員や管理者が確認し労働実態にあっているかを判定しながら勤怠管理を進めることができます。
仮にログと労働実態が違う場合は理由を記載した上で修正を行うことで、従来の勤怠管理ツールでは煩雑化してしまう客観的記録と打刻の乖離チェックを省略でき、より効率的に適切に勤怠を管理できるツールです。
上場・IPO準備・ベンチャー企業を中心に、「効率的な労働時間の把握」と「法令遵守」を両立したい企業に導入されています。
詳しくは 無料デモ・導入相談からお気軽にお問い合わせください