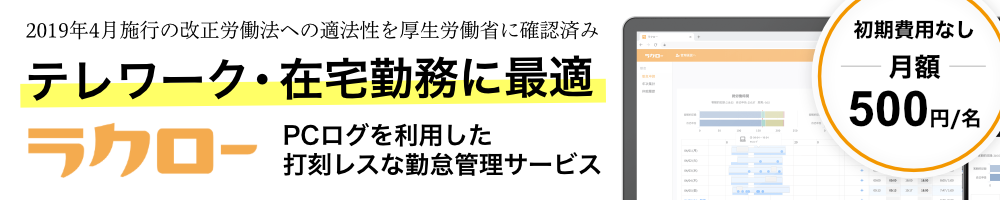本記事では、パート・アルバイトの残業代に関する基本的な考え方、具体的な計算方法、そして残業をさせる際の法律上のルールについて、詳しく解説していきます。
残業代の未払いは、単なる計算ミスでは済まされない大きなリスクを伴います。
正しい知識を身につけ、適切な労務管理を行いましょう。
パート・アルバイトでも残業代の支払いは必要!
結論から申し上げると、パート・アルバイトであっても、会社が定めた労働時間を超えて働いた場合や、法律で定められた労働時間を超えて働いた場合には、残業代の支払いが必要です。この「残業」を正しく理解するためには、「法定労働時間」と「所定労働時間」という2つの言葉の違いを理解することが不可欠です。
1.法定労働時間と所定労働時間の違い
「法定労働時間」とは、労働基準法32条で定められた労働時間の上限です。原則として「1日8時間、1週40時間と定められており、この時間を超えて労働させるには、後述する36協定の締結など、法律上の手続きが必要となります。
一方、「所定労働時間」とは、会社と労働者の間で結ばれた労働契約によって定められた、その会社独自の労働時間のことです。例えば、「1日5時間、週3日勤務(週15時間)」といった契約で働いている場合、この「1日5時間、週15時間」が所定労働時間となります。もちろん、この所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で設定しなければなりません。
この2つの労働時間の違いが、支払うべき残業代の割増率に関わってきます。
2.所定労働時間を超えた場合の残業代
まず、契約で定められた「所定労働時間」を超え、かつ法律で定められた「法定労働時間」の範囲内で収まる残業についてです。これを一般的に「法定内残業(法定時間内残業)」といいます。
例えば、所定労働時間が「1日6時間」のパートタイマーが、会社の指示で「1日7時間」働いたとします。この場合、所定労働時間を1時間超えていますが、法定労働時間である「1日8時間」は超えていません。
この法定内残業の1時間分については、法律上、賃金を割り増しする義務はありません。したがって、通常の時給と同額(1.0倍)の賃金を支払えば、法律上は問題ありません。
ただし、会社の就業規則などで「所定労働時間を超えた勤務については、〇%の割増手当を支払う」といった独自のルールを定めている場合は、その定めに従って支払う必要があります。
3.法定労働時間を超えた場合の残業代
つぎに、「法定労働時間」を超えて行われた残業についてです。これを「法定外残業(法定時間外労働)」といい、労働基準法37条に基づき、2割5分(25%)以上(月60時間超の法定外残業については5割(50%)以上)の割増賃金を支払う義務があります。
例えば、所定労働時間が「1日8時間」のアルバイトが、会社の指示で「1日9時間」働いたとします。この場合、法定労働時間である「1日8時間」を1時間超えています。この1時間については、通常の時給に25%を割り増しした賃金(時給 × 1.25)を支払わなければなりません。
これは、所定労働時間が短いパートタイマーにも同様に適用されます。例えば、所定労働時間が「1日6時間」のパートタイマーが、繁忙期に「1日9時間」働いた場合を考えてみましょう。
・実労働9時間のうち、最初の6時間:所定労働時間内(通常の時給)
・6時間を超え8時間までの2時間:法定内残業(通常の時給 × 1.0)
・8時間を超えた1時間:法定外残業(通常の時給 × 1.25)
このように、パート・アルバイトであっても、1日8時間・週40時間を超えて働かせた分については、法律で定められた割増率以上の残業代(割増賃金)を支払う必要があります。
残業代の計算例
それでは、具体的なケースを基に残業代の計算方法を見ていきましょう。ここでは、時給1,200円のパート・アルバイトの方を例に計算します。
基本的な計算式は以下の通りです。
「残業代 = 時給 × 割増率 × 残業時間数」
1.1日の労働が8時間以内だった場合
【ケース1】
・所定労働時間:1日5時間、週5日勤務(週25時間)
・ある日、2時間残業して合計7時間働いた。
この場合、実労働時間の7時間は法定労働時間である「1日8時間」の範囲内に収まっています。したがって、この日の残業2時間分は「法定内残業」となります。
≪計算式≫
・通常の賃金:1,200円 × 5時間 = 6,000円
・残業分の賃金(法定内残業):1,200円 × 1.0 × 2時間 = 2,400円
・この日の賃金合計:6,000円 + 2,400円 = 8,400円
割増賃金の支払いは不要ですが、所定労働時間を超えて働いた2時間分の時給は支払う必要があります。
2.1日の労働が8時間超、1週間の労働が40時間超だった場合
【ケース2】
・所定労働時間:1日7時間、週5日勤務(週35時間)
・ある日、3時間残業して合計10時間働いた。
この場合、実労働時間の10時間は、法定労働時間である「1日8時間」を2時間超えています。
≪計算式≫
・所定労働時間分の賃金:1,200円 × 7時間 = 8,400円
・法定内残業分の賃金:1,200円 × 1.0 × 1時間 = 1,200円
・法定外残業分の賃金:1,200円 × 1.25 × 2時間 = 3,000円
・この日の賃金合計:8,400円 + 1,200円 + 3,000円 = 12,600円
労働時間が週40時間を超えた場合も同様です。例えば、1日7時間×週6日勤務した場合、週の合計労働時間は42時間となり、法定労働時間(40時間)を2時間超えます。この2時間分については、1日の労働時間が8時間を超えていなくても、割増賃金の支払いが必要です。
3.法定休日労働があった場合
労働基準法35条では、労働者に週に少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることを義務付けています。これを「法定休日」といいます。この法定休日に労働(法定休日労働)させた場合、3割5分(35%)以上の割増賃金を支払わなければなりません。
【ケース3】
・日曜日を法定休日と定めている会社で、業務の都合上、日曜日に8時間労働した。
法定休日の労働には、「法定内残業」「法定外残業」の区別はありません。労働した時間すべてが3割5分以上の割増の対象となります。
≪計算式≫
・休日労働分の賃金:1,200円 × 1.35 × 8時間 = 12,960円
・この日の賃金合計:12,960円
なお、会社が週休2日制(例:土日休み)を導入している場合、どちらか一方が法定休日、もう一方は「法定外休日(所定休日)」となります。法定外休日の労働は、法定休日労働の割増(3割5分)の対象にはなりませんが、その労働によって法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた分については、法定時間外労働として2割5分の割増が必要になる点に注意が必要です。
4.深夜労働があった場合
午後10時から午前5時までの間に労働させることを「深夜労働」といいます。この時間帯の労働に対しては、2割5分(25%)以上の割増賃金を支払う必要があります。
【ケース4】
・所定労働時間が午後2時から午後10時まで(休憩1時間、実働7時間)のアルバイトが、1時間残業して午後11時まで働いた。
この場合、実労働時間は合計8時間となり、法定労働時間の範囲内です。しかし、深夜労働があるため、割増賃金の支払いが必要です。
≪計算式≫
・所定労働時間分の賃金:1,200円 × 7時間 = 8,400円
・法定内残業分の賃金:1,200円 × 1.0 × 1時間 = 1,200円
・深夜労働分の賃金(午後10時~11時):1,200円 × 0.25 × 1時間 = 300円
・この日の賃金合計:8,400円 + 1,200円+ 300円 = 9,900円
もし、この残業が「法定時間外労働」かつ「深夜労働」であった場合は、割増率は5割(50%)となります(25% + 25% = 50%)。また、「法定休日労働」かつ「深夜労働」であった場合は、割増率は6割(60%)となります(35% + 25% = 60%)。
残業時間の上限はあるの?
パート・アルバイトであっても、無制限に残業させられるわけではありません。労働者の健康を守るため、正社員同様、時間外労働の上限が定められています。
1.時間外労働は月45時間、年360時間が上限
労働基準法では、法定時間外労働の上限は、原則として「月45時間、年360時間」と定められています。これは、正社員やパート・アルバイトといった雇用形態に関係なく適用される上限です(管理監督者など一定の場合を除く)。
臨時的で特別な事情がある場合に限り、労使の合意(特別条項付き36協定)があればこの上限を超えることは可能ですが、その場合でも、
- 法定時間外労働時間が年間720時間以内
- 法定時間外労働時間が月45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間)を超えられるのは、年6回まで
- 法定時間外労働時間+法定休日労働時間が、単月100時間未満
- 法定時間外労働時間+法定休日労働時間が、2か月ないし6か月平均で80時間以内
といった上限があるため、これを超えないように労働時間管理を行うことが大切です。
法定時間外労働の詳細については、以下の記事もご参照ください。
2.パート・アルバイトでも時間外労働をさせるには36協定の締結が必要
そもそも、企業が労働者に法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりするためには、事前に「時間外労働・休日労働に関する協定書」(いわゆる「36(サブロク)協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
この36協定は、会社の労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者との間で、書面によって締結する必要があります。
パート・アルバイトであっても、36協定がないと法定時間外労働や休日労働をさせることができないため、留意が必要です。もし36協定を届け出ずに法定時間外労働や休日労働をさせた場合、労働基準法違反となり、罰則の対象となります。
36協定に関する詳細は、以下の記事もご参照ください。
パート・アルバイトに残業代を支払わないとどうなる?
1.パート・アルバイトであっても残業代未払いは違法!
これまで解説してきた通り、パート・アルバイトであっても残業代の支払いは必要であり、残業代の未払いは、労働基準法違反となります。
労働基準法違反となった場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されるおそれがあります(労働基準法119条1項)。
さらに、労働者から裁判を起こされた場合、裁判所は、企業に対して未払い残業代の支払いに加え、それと同額の「付加金」の支払いを命じることができます(労働基準法114条)。つまり、本来支払うべきだった金額の最大2倍を支払うリスクがあるのです。また、遅延損害金も発生することになります。
これらの金銭的な負担は、企業の経営に大きなダメージを与えかねません。
2.違法にならないようしっかり労働時間管理をすることが必要
このような事態を避けるためには、正確な労働時間の管理が重要となります。
具体的には、
- タイムカード、ICカード、勤怠管理システムなど、客観的に記録が残る方法で労働時間を記録、管理する。
- 上長の方が「これ以上残業するな」と言いながら、過剰な業務量を課して労働者がサービス残業せざるを得ないような状況を作らない。
弊社の「ラクロー」はPCログなどの客観的記録をベースに把握した労働時間を、従業員や管理者が確認し、労働実態に合っているかどうかを判定しながら勤怠管理を進めることができる勤怠管理ツールですが、パート・アルバイトといった多様な働き方にも対応しており、法定外・所定外・深夜等の時間数も自動で算出されます。
また、賃⾦未払いのよくあるケースとして「退勤後にも仕事をしていた」「休⽇なのに社内チャットでやりとりが⾶んでいる」などが挙げられますが、こういった場合もラクローならきちんとログが残るため賃金未払いのリスクを低減できます。
詳しくは無料デモ・導入相談からお問い合わせください