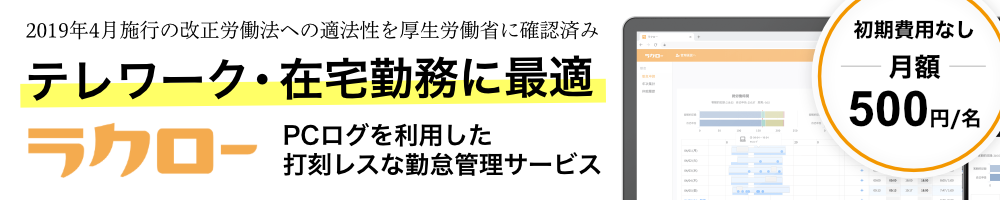今回は、IPOを目指す企業に必要な労務管理体制について、寺島戦略社会保険労務士事務所 所長 寺島 有紀 先生にお伺いした重要なポイントをまとめてご紹介したいと思います。
企業ステージに合わせた労務管理の必要性
IPOにおいて労務管理は最近かなり厳しく見られています。
こちらの図で、企業ステージとそれぞれのステージにおいて労務関連で義務付けられていることを表示しておりますが、ご覧の通り「労働者が増えるほど、やらなきゃいけないこと」が増えていくという傾向があります。
ベンチャー企業は急成長で大きくなっていくという特徴があると思います。
従業員人数が10名未満のような時は、みな知人等の創業メンバーで構成されていることも多く、仮に労働基準法が守れてなかったとしても、それが労務トラブルにまでつながるということは少ないかもしれません。
ただ、企業が成長フェーズに入ってくると「全く知らない人を採用する」というフェーズがやってきます。
その時初めて「36協定どうなってますか」とか「未払い賃金があるのではないですか」等の指摘を従業員から受けたりするケースもあるのではないかと考えます。
そこから、「いよいよまずいな、ちゃんと労務をやっていこう」と意識が変わり、勤怠システムの導入などもきちんと整備をするという企業が多いように思います。
上場を見据えるベンチャーが留意したい主要4ポイント
上場の際にはまず監査法人契約があり、証券会社のレビューを経て東証の審査に進んでいきますが絶対に見られる論点が4つあります。
1点目がいわゆる賃金帳簿、出勤簿、労使協定、規程類が整備されているかです。外形的にきちんと整っているかというところが一番です。
2点目はそこまで多くありませんが、社会保険・労働保険の加入漏れです。例えば試用期間中は社会保険に加入させないというような運用をしている会社がたまにありますが、このような場合には遡って加入させてくださいということになります。
3点目が一番重要で、未払賃金です。証券会社などに聞かれることのほとんどすべてがこの3点目に直結することになります。
4点目は労働法にきちんと対応しているかどうかです。労働法はとても法改正が多いのでそういったものにしっかりと対応できているかというものが見られます。
IPO準備における労務管理で注意すべきポイント1 法定帳簿・規定・労使協定の整備
法定帳簿
出勤簿や労働条件通知書等をそれぞれ法令で決められた法定保存期間、きちんと保管しておく義務があります。そういったものが揃っているかどうかを見られます。
規程
「就業規則・賃金規程・育児介護休業規程」は全ての会社にあるべきものです。他にもリモートワーク・在宅勤務で光熱費等の負担について取り扱うリモートワーク規程や出張旅費規程、従業員規模が大きくなるとストレスチェック規程なども策定が求められていきます。
労使協定
労使協定は非常に重要で、上場準備企業は必ず必要な労使協定が全て揃っているかを見られます。まずは時間外労働、休日労働の労使協定を結んでいなければいけません。36協定についてはまた後で説明しますが、時間外労働をさせるためには必ず整備されていなければならず、一年に一回の更新が必要です。時間外労働が何時間かを把握するために管理をしているわけでもあります。
他にも諸々ありますが、ベンチャー企業で多く利用されているフレックスタイム制や専門業務型裁量労働制等も労使協定がないとできません。企業としてこうした柔軟な労働時間制度を利用しようと思うと労使協定が必要になります。
IPO準備における労務管理で注意すべきポイント2 社会保険の未加入者
ベンチャーによくあるのが代表取締役が実は社保に入っていないパターンと、試用期間中の社員を加入させていないパターンです。試用期間中であっても週所定労働時間が資格取得要件を満たす場合には入社日から加入しなくてはいけません。
学生インターンの場合、昼間の大学生には雇用保険は必要ありません。ただ、週所定労働時間が正社員の4分の3以上ある場合は健康保険・厚生年金保険には加入させる必要があります。ここを知らない会社が結構あり、未加入のままにしているところがあります。
IPO準備における労務管理で注意すべきポイント3 未払い賃金が発生していないか
「未払い賃金が発生していないか」というのが上場準備上最も重要な論点です。 未払賃金の発生要因ですが、次の4点が大きい未払賃金の発生要因です。
- 固定時間外手当の取扱い
- 管理監督者の定義
- 裁量労働制の取り扱い
- 労働時間の取り扱い
1つずつ見ていきましょう。
1.固定時間外手当の取扱い
「固定時間外手当制度」とはあらかじめ一定時間分の残業代を手当として含ませているものです。だいたい月40~45時間ぐらいで設定しているベンチャー企業が圧倒的に多いです。求人の際は基本給だけ掲載するより、基本給に加えて固定残業代があった方が総額が大きくなり見栄えがよく採用力アップになるというところも固定時間外手当が多く導入されている理由かと考えます。
しかも、基本給50万円とするより、基本給40万円・固定残業代10万円と切り分けておいた方が、残業代のベースに固定残業代を含まなくて良いため、残業代の単価を下げることができます。
後は、割増賃金の計算も簡便化できます。固定残業代として45時間分入っている場合、勤怠上30時間しか働いていない時には時間外割増賃金については追加支給しなくていいので、給与計算が簡単になります。
ただ、まだ間違った運用をしている会社も多いのが実情です。有効なものは基本給と固定時間外手当がちゃんと書き分けられていて、更に固定時間外手当は○○時間相当であると時間までも明記されていることです。
また固定残業代を超える残業代は支給しない、という会社もたまにありますが、それは完全にアウトです。明記した固定時間外手当金額を超える時間外があるのであれば、必ず追加支給しなければいけません。
2.管理監督者の定義
「管理監督者」は労働基準法に規定があり、事業の種類にかかわらず監督管理の地位にある方には労働時間規定を適用しないとあります。これが一般に「管理監督者には残業代を払わなくてもよいらしい・・・」という根拠になっているわけです。
しかしここで気を付けたいのが、労働基準法上の管理監督者=会社の管理職ではないということです。企業が役職者だと主張しても、それは単なる対外的な役職に過ぎないわけで、労基法上の定義に則っていなければ管理監督者ではないということになってしまいます。
経営側からすれば、残業代を支払わなくてよいのですからできる限りみんな管理監督者にしたいですよね。しかし、労基署が入り「管理監督者」ではないと否定された瞬間、今まで支払ってこなかった残業代を遡って支払う必要があり、その金額は大変な未払賃金になります。
この「管理監督者の要件」については直近の裁判例等をみても昨今、非常に要件が厳しくなっているように思います。
管理監督者性を判断する際に重要な点として、待遇要件があります。待遇というのは社内の中での相対的な待遇になります。少なくとも残業代がつく直近の部下よりも賃金が下回ることがないのであれば問題ないと考えてよいでしょう。
次に遅刻・早退の扱いです。管理監督者が残業代がでないというのは、裏を返せば時間管理の裁量があるから引かれないという立て付けです。なので、遅刻・早退の時間を給与で引かれるということがあれば、労働時間の自由がないということになり、控除はできないことになります。
この上記2点については多くのベンチャー企業も満たしているところが多いと思います。
ただ残りの1点目「経営者と一体的な立場となって仕事をする」はなかなか満たせていない企業は多い印象です。
事実上の経営の裁量はなく、経営者と一体的な立場にはないと見なされることが多いです。
少なくともベンチャー企業の場合、経営会議に出席する立場にあるかどうかです。 IPO準備企業はあえて経営会議に管理監督者を出席させ、発言の議事録まで取ったりします。
管理監督者制の要件は、このように厳しく判断されるため、10名20名の会社において大部分が管理監督者だと言ったとしても通常認められないものと考えます。
上場準備企業においては、大体、管理監督者は全雇用契約従業員の10%くらいにとどめておくことが安全であるとは考えています。
3.裁量労働制の取り扱い
裁量労働制を利用している企業も多いと思いますが、裁量労働制とは労働時間を実労働ではなく一定の時間としてみなす制度です。端的に言えば、実労働が15時間でも13時間でも労使協定において8時間としてみなすと決めれば8時間としてみなせる制度になります。
裁量労働制には「専門型」と「企画型」の二種類があります。
専門型は19業務に限り、労使協定の策定・届出、就業規則の改定手続きで導入できるもので、ベンチャー企業で活用しているところも多いと考えます。
裁量労働制で労働時間を8時間とみなした場合、時間外労働という概念がないということになりますが、いくら裁量労働制だからといって実労働時間を管理しなくてもよいということではなく、きちんと労働時間管理はしていなければならないことには留意が必要です。
なお、裁量労働制もそうですが管理監督者についても労働時間を把握する義務はありますので、そこは重要な点として覚えておいていただきたいところです。
経営側にとっては裁量労働制を活用するメリットは多いわけですが、ただ、この裁量労働制の適用が適正でないとし否定されてしまう場合、割増賃金等は実労働時間通り払う必要があることになります。そのため裁量労働制が否定されると膨大な未払賃金が発生する可能性が起こり得ます。
上記のように諸々ありますがいくつか挙げるとまずは名の通り、裁量がある人にしか適用できません。例えばSEの中でも単にプログラムを打つだけの人や、新卒1年目に適用させる等していると新卒でなぜ裁量と専門性があるんだ、となります。新卒一年目に適用させるのは危険です。職歴として少なくとも大体2年目以上でなければ厳しいと考えます。
みなし時間も毎日14・15時間働いているのに8時間としてみなしていると、労働基準監督署の調査等の場合でも、「みなし時間の設定がおかしい」ということになることがあります。
また、裁量労働制でも深夜と休日の割増賃金は逃れられません。つまり裁量でも深夜・休日は絶対カウントしてその通り割増賃金を払う必要があるため、実労働時間はそのためにも把握していなければなりません。
裁量労働制だからと何の割増賃金も払わなくてよいと勘違いしてる会社も未だに多いですが、それは間違っています。
あとは業務が裁量労働制の適用業務であるかです。 SEやデザイナーなど限られた19業務にしか適用できないので、例えばコーポレート部門の方に専門型裁量制を適用することはできません。そのため適用業務がおかしくないかということがみられます。
裁量労働制の場合、健康確保措置・苦情処理措置を講じる必要があります。つまり実勤怠は把握してるわけですから、過労の人がいたら有給を取得させるか特別休暇を付与する、そういったものを労使協定に盛り込む必要があります。裁量労働適用者から苦情が来た時の窓口が設置されているかも必要になってきます。
専門型も企画型も裁量労働制という名がつくものは労使協定を労働基準監督署へ提出します。
<ハードルが高いと言われる企画型裁量労働制について>
企画型裁量制についてですが、専門業務型裁量労働制と異なり業務に縛りがなくなるため、専門裁量では適用業種とならない業務に対しても裁量労働制が使えるといったメリットがあります。一方で、企画業務型裁量労働制の導入には、労使委員会というのを組織し、導入には労使委員会で決議する必要がありますし、また定期報告というものを6ヶ月に1回、労基署に届出をする必要があります。
このように専門裁量よりも導入のハードルは高く、ベンチャー企業でもあまり積極的に導入しているところは多くありません。
4.労働時間の取り扱い
労働時間とは会社にいる時間だけではなく、労働者が会社からの指揮命令を受けていると客観的に判断できる時間は全て労働時間になります。
最近、勤務時間外にslackやメッセンジャーなどのチャットツールを使用した連絡等が取り上げられるようになってきました。休日だけど忘れないうちに社員にslackで流しておこうみたいなことをするとそれに対して社員が返信を行う場合には、労働時間制が問題になります。
時間外・休日のやり取りがあると、それは労働時間とカウントされる可能性は大いにあります。
そのためIPOを準備している会社は休日等に送る場合、タイトルに「即レス不要」のようなものを入れ、即レスを求めていないことを周知したりするルールを設けているところもありますし、もっと厳しいところでは休日等にslackは開かないようにと周知をするところもあります 。
IPO準備における労務管理で注意すべきポイント4 コンプライアンス違反(パワハラ、ダイバーシティ)
コンプライアンス遵守についてですが、労働法とひとくくりにいっても、実に多くの法律があります。労働基準法という企業の労務のベースとなる法律の他にも、関係する法律は多岐にわたるので、これが労務がややこしいゆえんです。
安全衛生管理体制がきちんと整っているか
例えば労働安全衛生法では、企業が適切な安全管理体制を整備するための各種義務規定があります。例えば、ITベンチャー企業に関連するものとしては、産業医や衛生管理者を置いているかとかですね。
IT業種の場合、多くの場合従業員が50人を超えた時から安全衛生管理体制が必要になってきます。産業医を選任しているかや、衛生委員会を設置し月に1回衛生委員会をしたりなどです。他にも健康診断を労基署に報告したり、ストレスチェックといって従業員の心理的な負荷、つまり精神的に疲労していないかということをチェックする義務があったりします。
様々なタイプのハラスメントに対し適応しているか
2020年6月にパワーハラスメント防止のための法律ができたことも話題になりましたが、ハラスメントに関しても上場準備企業はかなりセンシティブに考えてるところが多いです。
ハラスメントは訴訟等が起きると特に知名度のある企業等の場合、Twitterなどで内容が大きく伝わるので、会社の評判が下がったりと外部に漏れるとダメージが大きいものではあります。
ハラスメントには色々な種類がありますが職場で起こりやすいセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント、ケアハラスメントは各種法律で軒並み禁止されています。
会社にはそういうものを全部防止しなければいけない義務があります。
雇用契約の形態があっているかどうか
偽装請負問題もベンチャー企業によくある問題です。ベンチャー企業は業務委託者を活用することが多いかと考えます。労働者には加入が求められる社会保険にも入らなくて良い上、契約終了がしやすいというのもその理由かと思います。
名称はフリーランス・業務委託なのに実際は指揮命令をしている、勤務時間の管理もしているなど、このようになるとそれは業務委託契約というより実態は労働者なのでは、偽装請負状態なのではといったことになってしまいますので、こうした状態が発生しているのであれば、上場準備の時に是正が求められます。
ダイバーシティに関連する労働関連法が守られているか
人種・国籍・性別・年齢・障害・性的指向等、多様性に関しても実は労働法上多くの規制があります。
外国人就労者であれば在留資格を確認しているか、外国人を雇用する際に必要な雇用届をきちんと提出しているかを確認されます。
障害者については法定雇用率を未達成の場合は、1人当たり5万円の障害者雇用納付金を納めることになります。足りていない人数に応じて納付するという制度、障害者雇用という義務があります。
高年齢者については60歳未満は定年にできません。60歳以上でなければいけないとあり、更に希望者は65歳まで全員再雇用と義務づけられています。
コンプライアンスについても本当に色々とありますが、こういう法律関係は全般も守っていかなければなりません。
会社として就業規則の中で事業主の方針を周知するということは一つのハラスメント防止策です。つまりうちの会社ではハラスメントはあってはならない、ということを就業規則の中に盛り込んでおくことです。セクハラしていはいけない、パワハラしてはいけないなど事業主の方針を明確化し、また、ハラスメントの相談窓口の設置等も必要です。
さらに、会社として定期的にハラスメント研修など行っていると、会社はハラスメント防止のための方策を各種講じていたという証にもなります。こうしたハラスメントへの対策を兼ねて、ハラスメント・コンプライアンス研修を定期的に実施しているところは、上場準備企業でも多いです。
ログベースで労働時間を管理するラクローのご紹介
「ラクロー」はPCログ等の客観的記録をベースに労働時間を管理し、実態が客観的記録と異なる場合に理由を添えて自己申告時間を修正することで労働時間管理にかかる手間や、未払い残業代など労働時間管理に関わる経営リスクを低減できます。
上場審査における労務監査でも最重要ポイントとなっている未払い残業代ですが、打刻レスのラクローでは打刻と客観的記録との乖離が発生しないため、賃金や残業代の未払いも発生せず、 IPOに向けた適正な管理を実現します。
詳しくは無料デモ・導入相談からお問い合わせください。